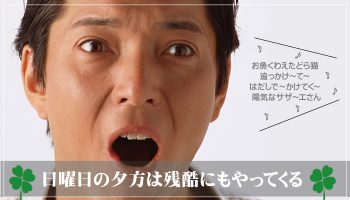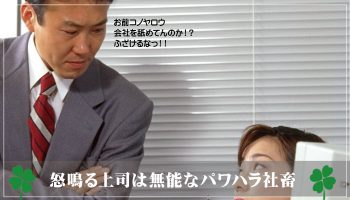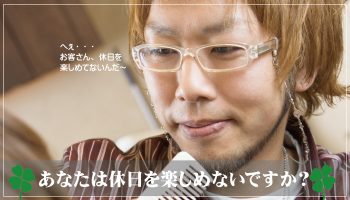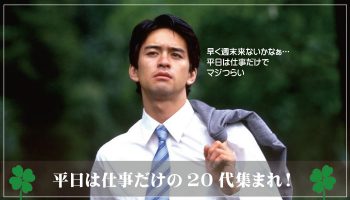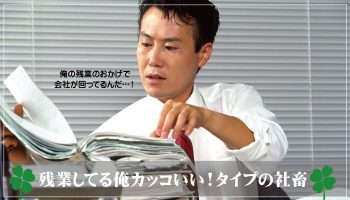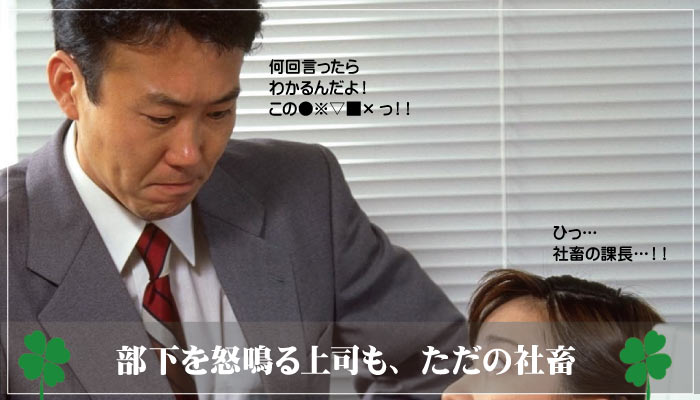
「部下を怒鳴りつけてしまって、いつも部下が委縮してしまう…」
「部下を褒めるようにしているんだけど、部下になめられてしまう。部下にどのように接すれば良いのかわからない」
このような悩みを持つ上司は多いと思います。
部下とうまく接することができないと、部下は仕事での結果を出すことができません。
そうすると、あなた自身の会社からの評価が下がります。
それはヤバい!!!
大丈夫です。
部下への正しい接し方を実践すれば、部下のやる気を引き出して、仕事で結果を残すことができます。
そして、あなたは部下を管理できる「できる上司」になることができるんです。
部下への正しい接し方のキーワードは、
横から目線!
これであなたは怒鳴る上司・褒める上司から卒業できます。
つまり、社畜ではなくなるんです。
部下に信頼されるし、会社からの評価も上がるし、理想の「できる上司」・「カッコいい上司」になることができますよ。
ここまで読んで、
「え?怒鳴る上司と褒める上司は同じ扱い?」
と思った人もいると思います。
そうなんです!
怒鳴る上司も褒める上司も、「自分の評価を気にするだけの社畜」という点では同じなんです。
だから、怒鳴る上司も褒める上司も、部下への正しい接し方を身につければ、どちらも社畜から卒業することができますよ。
部下を怒鳴る上司・褒める上司は勇気づけをすれば社畜から卒業できる!
社畜から卒業するには、
部下の勇気づけ
ができる上司になれば良いんです。
まずは10日間、勇気づけを意識した接し方をしてみましょう。
「勇気づけって何?」
というあなたのために、勇気づけのための正しい部下への接し方を説明していきます。
怒鳴ること、褒めることは上から目線の勇気くじき
部下を怒鳴ることも褒めることもNGです。
なぜなら、怒鳴ることも褒めることも、
上から目線で勇気くじき
となる行為だからです。
部下をパワハラのように怒鳴りつけると、
「俺が上の立場でお前は下の立場だ」
と相手に誇示することになります。
そして、怒鳴りつけることで、部下は萎縮してしまいます。
萎縮した部下は、自主的に動くことができず、指示されたことしかできない指示待ちばかりをする部下になってしまいます。
また、褒める行為というのは、一見良い行為に見えますが、
「立場が上の俺が、お前を評価してあげている」
と自分の力を誇示する行為でもあるのです。
あなたは部下をコントロールするために褒めるている。
このあなたの魂胆を部下に見透かされて、あなたは部下の信頼を失います。
信頼できない上司とは一緒に働きたいとは思いません。
バカらしく感じて、指示されたことだけ、しかも必要最低限のことしかしない部下になってしまうのです。
上から目線で偉そうにされたら、誰だって不快に思いますよね。
そして、いくら会社内での立場は上と言っても、あからさまに上から目線で接してくる上司には、誰もついていこうとはしません。
上から目線の上司は
「パワハラだ!」
と訴えられたり、
「バカらしい(笑)」
と舐められて終わりです。
だから、怒鳴ること・褒めることは勇気くじきの行為であり、部下のためにはならず、部下のやる気や能力を削ぐ行為になるのです。
勇気づけの接し方は横から目線
部下のやる気や能力を引き出すような接し方、つまり「勇気づけ」になる接し方とは、どんなものなのか気になりますよね。
部下を怒鳴ってもいけない。
部下を褒めてもいけない。
「じゃあ、どうするんだよ?」
というあなたの反論・疑問が聞こえてきそうです。
部下の勇気づけになるための接し方は、
怒鳴らない・褒めない
です。
これが基本になります。
怒鳴らない・褒めないという接し方は、上から目線にはなりません。
もちろん、へりくだった下から目線でもありません。
対等な横からの目線になりますので、部下に不快感を与えることはないのです。
部下が不快に思わなければ、部下のやる気を引き出す勇気づけができます。
横から目線というのは、事実を伝えるだけ、そして主観や感想を言うだけ。
評価をすることはありません。
これでOKです。
では、営業のプレゼンが迫っているのに、なかなかプレゼン準備が進んでいない部下への接し方を例にとって見てみましょう。
パターン1 事実を伝える
「今週金曜日がプレゼンだよ」
このように伝えれば、事実を伝えているだけで、部下を評価していません。
パターン2 事実+主観を伝える
「今週金曜日がプレゼンだよ。僕は準備が間に合うかどうか不安だな」
これは事実を伝えて、主観・感想を伝えていますね。
「君は○○だ」
と伝えるのは、上から目線になります。
でも、
「私は○○だと思う」
と主観や感想を伝えるのは、横から目線になりますので、勇気づけになるのです。
この時に大切なことは、感情をそのままぶつけるのではなく、裏を読むことです。
あなたは、部下がプレゼンの準備をなかなか進めないことに苛立ち、怒りを覚えることもあるでしょう。
この感情を持つのは仕方がないことです。
ただ、
「遅すぎるんだよ!なんでそんなに遅いんだ!
と苛立ちや怒りをそのままぶつけると、威圧的になりますので部下は萎縮して指示待ちしかできなくなりますし、反感を持つこともあるでしょう。
だから、アンガーマネジメントをした後に、自分の感情の裏を読むのです。
上司になったら、アンガーマネジメント(怒りのコントロール)を身につける必要があると聞いたことがあると思います。
アンガーマネジメントの基本に、「怒りの衝動は6秒間我慢する」というものがあります。
怒りのピークは6秒間だけ。
だから、まずは怒りが湧いてきた時は、その場からすぐに離れて6秒間我慢する。
そして、怒りの衝動が静まり冷静になったら、自分の感情の裏を読むために、次のことをあなた自身に問いかけてみましょう。
「なんで苛立つのか?」
「なんで怒りの感情が湧いてくるのか?」
これを考えてみましょう。
そうすれば、
「間に合うかどうか不安だから、苛立つし、怒りが湧く」
とわかるはずです。
「間に合うかどうかが不安」
というのが、あなたの裏の感情になります。
裏の感情を伝えれば、威圧的にはなりません。
むしろ、心配・不安・恐怖・悲しみ・寂しさなどの
「助けてあげたい」
「手を差し伸べてあげたい」
と思わせるような感情を相手に伝えることができますので、勇気づけになるのです。
もし、これでも部下が動かないなら、上司であるあなたは、解決策への提案をすると良いでしょう。
ここでのポイントは、あくまで提案にすること。
命令ではありません。
パターン3 事実+主観+提案を伝える
「今週金曜日がプレゼンだよ。僕は準備が間に合うかどうか不安だな。今日から準備を始めたほうが良いと思うけど。」
このように提案をすれば、相手は悪い気はしませんよね。
ここでのポイントは、提案部分は独り言のようにつぶやくことです。
上司という立場上、面と向かって提案すれば、それは相手に「命令された」と取られかねません。
だから、独り言のように呟いたほうが効果的なのです。
そして、提案する時には原因分析が必要ですよね。
なんでプレゼンの準備が進んでいないのか、その原因分析は上司としてしっかり行うべきです。
でも、原因ばかりを指摘してはいけません。
原因だけを指摘すると、部下を責めることになるからです。
あなたが原因を指摘したら、そこはまるで裁判の尋問や警察の取り調べのような雰囲気になるでしょう。
これは、間違いなく勇気くじきの行為ですよね。
ただ、原因分析をすることは大切で、部下がその原因に気づいていないのであれば、それを指摘することは重要です。
だから、原因を指摘する必要があるのなら、提案という形で、サラッと指摘する程度にする。
原因を指摘してネチネチ責めたら、まさにあなたはパワハラ上司!
基本的には原因を指摘しない。
必要なら提案という形でサラッと触れる程度にするようにすると良いと思います。
さらに、解決法や原因の提案は他の案を部下が提案してきたら、すぐに引っ込めましょう。
「今日から準備を始めたほうが良いと思うけど」
とあなたが呟いた後に、部下が
「明日からやります」
と言ってきたら、
「そうか、わかった」
と自分の案を引っ込めてください。
そうしないと、あなたが自分の案を部下に押し付ける形になってしまうからです。
もちろん、
「今週金曜日がプレゼンだよ。僕は準備が間に合うかどうか不安だな。準備が遅いなんて、ダメな奴だな」
のように部下を評価するのもNGですよ。
評価するのは、横から目線ではなく、上から目線になりますから。
現実では褒めることも必要
部下への正しい接し方は、横から目線で「怒鳴らない&褒めない」ことです。
横から目線で接することで、部下への勇気づけをすることができ、部下のやる気を引き出し、仕事のパフォーマンスを上げることができます。
上司が上から目線で接すれば、部下は動きません。
部下が動かないことに苛立ち、さらに上から目線で接するという悪循環に陥ります。
それに対し、上司が横から目線で接すれば、部下が自ら動くようになります。
部下が自ら動くことに手ごたえを感じた上司は、ずっと横から目線で接するようになるので、好循環になるのです。
ただ、現実問題として、
「まったく褒めない」
というのは、上司としてダメですよね。
褒めなければいけないケースもあると思います。
そういう時は、褒めてもOKです。
「は?さっき、褒めるのは上から目線だからダメって言ったじゃん!」
と思うかもしれません。
確かに、やみくもに褒めちぎるのはダメです。
ただ、褒めるべきところは褒めるようにする。
そして、褒めっぱなしにはしない。
これは鞭を使うわけではないので「飴と鞭」とは違いますが、褒めたらすぐに横から目線に戻る。
つまり、基本は横から目線で、必要最低限で褒める。
これが部下への正しい接し方なのです。
基本は見守る姿勢で
部下へ勇気づけをする時には、基本的には見守る姿勢が大切です。
部下を育てたい、指導して早く仕事ができるようになってほしいと思うかもしれませんが、あなたが積極的に指導するという方針はおすすめできません。
部下の自主性を重んじて、見守る姿勢を取りましょう。
そして、部下が自ら何らかの答えを出して自分で動くまでは、上司は口出しせず待ってあげてください。
そうすることが、部下の考える力や自主性を伸ばす方法なのです。
部下の考える力や自主性を伸ばすことができたら、それは間接的にあなたが指導しているようなものですよね。
積極的に指導すれば、あなたはウザい上司になるだけ
あなたから積極的に指導してしまうと、部下の自主性を潰すことになります。
過干渉になります。
「ウザい上司」になります。
さらに、
「教えてあげる」
という上から目線になり、横から目線で接していないことになります。
また、あなたが積極的に指導すると、部下は
「指導されている」
「やらされている」
と思いながら受け身の姿勢で仕事をすることになります。
そして、指示待ちしかできず、自主的には動けなくなってしまうのです。
受け身の姿勢では、学べるものも学べません。
何も吸収できず、何も身につけられません。
あなたの苦労は水の泡。
そして、あなたは
「指導してやったのに、結局何も学んでないじゃないか!」
と怒りを覚え、部下は
「指導してくれなんて頼んだ覚えはないのに、ウザいなぁ」
とうんざりするという悪循環を生みだします。
ただ、見守る姿勢は部下から
「何も教えてくれない上司」
「上司としての仕事をさぼっている」
と誤解を受けかねません。
だから、見守る姿勢を取る前に、部下にはあらかじめ、
「僕は君の解決能力が高いと思っている。だから、余計な口出しはしない。ただ、もし君が困ったら、全力でサポートするから、その時は遠慮なく言ってください」
のように伝えておきましょう。
相談・要請があった時だけヒントを与える
部下が仕事のことで悩んでいたり、行き詰っているのを見ると、手助けしたくなるかもしれません。
でも、部下から相談・要請がない場合は、口出ししないし、手助けもしない。
部下が自ら動くのを待つようにしましょう。
相談・要請があった時だけ、それに応える形で指導する。
その時は自主性を重んじて、指導してください。
例えば、
「このケースはどういう形で対処したら良いですか?」
と質問されたら、
「どうしたら良いと思う?君はどうしたいのかな?」
と質問を返してみましょう。
このように対処することで、質問してきた部下は自分で考える力を身につけ、責任感を持ち、自分の力で成長しながら自信を持つことができます。
また、部下を指導する時には、先ほど説明した
事実+主観+提案
の形で部下を導きましょう。
この時の「提案」はヒントを与える形にすると良いですよ。
- 今までの成功体験を伝える=前はこういう形でうまくいったけれど、どう思う?
- 今までの失敗体験を伝える=以前はこうやって失敗したんだよなぁ(独り言風に)
- 視点を変えるように伝える=君がクライアントだったら、どう思うかな?
- 制約をなくして考えさせる=予算無制限だったら、どういう案があるかな?
このように部下に気づきを与えるようなヒントを提案しましょう。
失敗から学ばせる
部下と接する時には、失敗から学ばせる意識を持つことも大切です。
「失敗」という言葉に敏感になっているサラリーマンは多いと思います。
失敗すれば上司から怒られるからですね。
ただ、失敗は悪いことではないんです。
人間は失敗から学び成長する生き物ですから。
失敗を恐れると、チャレンジすることができなくなります。
チャレンジしなければ、成功は減ります。
失敗することを恐れた部下は、指示待ちばかりの部下になりますよね。
チャレンジをすれば失敗は増えます。
でも、成功も増えるんです。
だから、失敗は悪いことではありません。
ただし、失敗から学ばなければ、その失敗は無意味なものになります。
上司は部下が失敗から学べるように接する必要があります。
失敗から学ぶためには、アドラー心理学の論理的結末という考え方が効果的です。
論理的結末は、ルールを決めて約束をする。
そして、その約束を破ったら、決めたルールに従って「当然の結末」を体験させるというものです。
このアドラー心理学の論理的結末は、子どものしつけに応用される考え方ですね。
- 幼稚園で友達とケンカしないという約束をした。友達とケンカをしたから家に連れて帰った。
- 朝寝坊せずに自分で起きると約束した。自分で起きられないが、約束したので親は起こさなかった。結局寝坊して、学校の先生にこっぴどく怒られることになった。
- 19時までに家に帰ってこないと夕食はないという約束をした。19時過ぎに帰ってきたので、その日の夕食はなしにした。
このようなものが論理的結末です。
簡単に言うと、自分のミスは自分で責任を持つということですね。
これを仕事に応用して、
- 遅刻をしないと約束する。遅刻をしたら、今の新規プロジェクトのメンバーから外す
- しっかり確認するように約束する。確認ミスをしたら、確認ミスを起こさないためのマニュアル作りをさせる
「失敗したから、こういう結果になってしまった」
ということを実際に体験させるようにすれば、部下は失敗から学ぶことができます。
この時の注意点は3つあります。
論理的結末は罰ではない
論理的結末と罰は違います。
「これをしたからこういう結末になった」
ということを納得できるものにしなければいけません。
「遅刻をしたら仕事に悪影響が出るからプロジェクトメンバーから外す」
これは納得できる結末ですよね。
それに対して、
「遅刻をしたら会社のトイレを1人で掃除してもらう」
これはただの罰でしかありません。
だから、失敗から学ばせるためには、罰ではない論理的結末を用意しましょう。
ネチネチ接しない
部下があなたとの約束を破ってしまった場合、あなたは明るく共感しながら、サラッと話しましょう。
「そうか。残念だ。次は頑張れよ」
という形ですね。
ネチネチと
「やっぱりできないと思ったんだよ」
「俺の言った通りだろう?」
のように言うと、部下は間違いなく傷つきます。
なぜなら、このように上司に言われたら、
「君には初めから期待していなかった」
と言われたようなものですから。
だから、部下を必要以上に傷つけないためにも、、明るくサラッとコメントして終わりにしましょう。
甘やかさない
論理的結末は失敗から学ばせる必要があります。
だから、甘やかしてはいけません。
部下が泣いても決めたルールの結末を変えてはいけないのです。
「部下が泣いて反省しているから、遅刻したけれどプロジェクトメンバーから外すのをやめる」
というのは、誰のためにもなりません。
部下は、
「泣けば許される。チョロイな」
と思って、またすぐに遅刻するでしょう。
だから、泣いても謝っても甘やかしてはいけないのです。
この接し方はお互いを信頼・尊重することが前提
正しい部下への接し方を説明していきました。
今まで怒鳴る上司や褒める上司だった30代の人は、ここまでの説明を見て、
「え?この接し方で大丈夫なの?うまくいくの?」
と不安になるかもしれません。
でも、大丈夫です。
この接し方なら、あなたは部下からも信頼され、会社からの評価もうなぎのぼりになるはずです。
ただ、1つ気を付けなければいけないことがあります。
この部下への接し方は、お互いに信頼・尊重していることが前提となっていることです。
この「怒鳴らない・褒めない」という横から目線の部下への接し方は、アドラー心理学の「課題の分離」がベースとなっています。
アドラー心理学は先ほども少し触れましたが、心理学者のアルフレッド・アドラーが提唱した心理学の体系のことです。
このアドラー心理学の中に「課題の分離」という考え方があります。
「課題の分離とは自分の課題と他人の課題は分けて考えるべき。自分の課題を一生懸命やれば良い。他人はコントロールできないのだから、他人の課題まで気にする必要はない。」
という考え方です。
これは、一見冷たい考え方のように思えますが、相手を信頼し、尊重して見守るという姿勢が根本にあるのです。
今回の部下への接し方で言えば、
「君を信じているから、僕は基本的に見守る姿勢でいる」
「僕はこう思うんだけど、どうかな?」
という見守りと主観+提案ですよね。
ここには信頼と尊重があるから、
「最終的にどうするかは君次第だよ」
というメッセージが隠されているのです。
だから、上司であるあなたは、まずは部下を信頼し尊重すること。
そこから始めていきましょう。
部下への正しい接し方ができない職場で働いているなら、転職を考えて!
怒鳴る上司や褒める上司は部下への勇気づけをするために、横から目線で接するようにすれば、社畜から卒業して理想のできる上司になることができます。
そして、あなたは会社の評価が高くなり、出世していくことができるはずです。
でも、あなたが理想のできる上司になりたくても、うまくいかない職場もあると思います。
横から目線で接していたら、あなたの上司から
「もっと部下に厳しく怒鳴るくらいで接しないとダメだよ」
「今の若者は褒めないと伸びないんだよ。とにかく褒めるようにしないと!」
のように言われてしまったら、どうでしょうか?
古い考えの職場や間違った方向に意識が高い職場だと、理想の上司になれませんよね。
そのような職場で働いていたら、あなたは一生社畜から卒業できません。
もし、あなたがそのような職場で働いていて、部下に横から目線で接することが許されないのあれば、転職を考えましょう。
あなたは一生社畜でいるのですか?
それとも、理想の上司になって出世する道を歩みたいですか?
どちらを選ぶかはあなた次第。
「俺は一生社畜で良いし…」
と思うなら、今の職場で社畜人生を歩みましょう。
「俺は社畜は嫌だ!出世するんだ!」
と思うなら、横から目線で接することができる職場に転職してください。
そうすれば、理想のできる上司になることができ、出世街道を歩んでいくことができます。
「30代で転職なんて大丈夫なのか?」
という心配はいりません。
人材不足の現代においては、30代でも転職できます。
管理職経験がある30代なら、今よりも良い条件のホワイトな職場に転職することができる可能性は高いです。
だから、社畜から卒業したいなら、転職することをおすすめします。
転職するなら、転職エージェントを使うことをおすすめします。
転職エージェントなら、キャリアアドバイザーが社風や職場の雰囲気、人間関係等を詳しく調べてくれるので、横から目線で部下に接することができるか、理想の上司になれる職場かなどを転職前にわかるんです。
また、今よりも好条件の職場もピックアップしてくれますので、あなたの転職が成功するように後押ししてくれるんです。
転職エージェントはすべてのサービスを完全無料で利用できますので、気軽に登録して、キャリアアドバイザーに転職の相談をしてみてください。
執筆者情報

- 天職エージェントは、厚生労働大臣から転職サポート(有料職業紹介事業)の許可を受けた(許可番号13-ユ-314851)株式会社ドリームウェイが運営するメディアです。転職サポートの経験を活かし、定期的なリライトや専門書を用いたファクトチェックなど、ユーザーに正確な最新情報を届けられるよう努めています。
最新の投稿
- 2022年12月21日看護師看護師の残業10時間以下の求人は注意点がたくさん?残業少なく働く方法!
- 2022年10月3日看護師看護師が4週8休以上の求人を選ぶ時の注意点6つ!お休み多めで働ける!
- 2021年3月23日看護師馬が合わない先輩看護師から受けるストレス、我慢するしかないの?
- 2020年11月11日看護師看護師の先輩が私にだけ冷たい?その感情は解消できる!